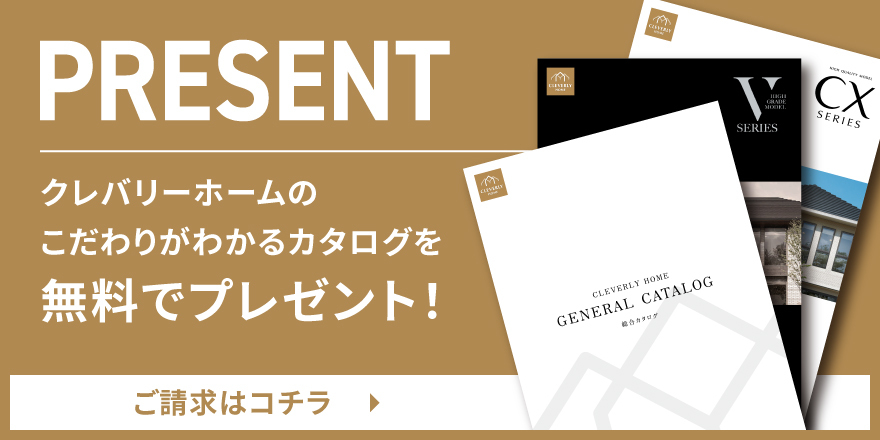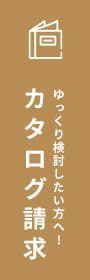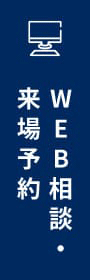注文住宅の住宅ローン基礎知識|流れや支払いタイミング、返済額シミュレーションも

注文住宅づくりでは、住宅ローンを含めた資金計画が重要になります。
住宅ローンを組むのが初めてだと、どうやって金額を決めるのか、いつ申し込むかなど、疑問や不安なポイントも多いですよね。
そこで今回は、注文住宅の住宅ローンを組む時に必要となる基礎知識を分かりやすくまとめます。
予算の決め方から審査、融資が実行されて支払いが始まるまでの流れを把握しておけば、注文住宅づくりがスムーズに進みます。
必要書類や注意点などの情報も解説しますので、ぜひ資金計画にお役立てください。
目次
注文住宅の住宅ローンの組み方

一般的な注文住宅の住宅ローンの組み方は、大きく分けると次の3種類です。
- 土地を現金で購入して建物のみ住宅ローンを組む
- 土地をローンで購入して住宅ローンに一本化する
- 分割融資で土地と建物の費用をまとめて借りる
具体的な流れをチェックする前に、まずは3つの住宅ローンの組み方の概要と違いを把握しておきましょう。
①土地を現金で購入して建物のみ住宅ローンを組む
すでに土地をお持ちの方や、自己資金で購入する予定の方は、建物のみ住宅ローンを組むことになります。
自己資金なら良い土地が見つかったタイミングですぐに購入でき、住宅ローンの手続きも簡略化できるのがメリットです。
ただし、土地購入で現金を使い切ってしまうと、住宅ローンの頭金が減って審査のハードルが高くなる可能性もあるため、バランスを考えることが大切です。
②土地をローンで購入して住宅ローンに一本化する
土地購入費用を自己資金でまかなうのが難しい場合、「土地先行融資」「つなぎ融資」などを利用して土地を購入し、後ほど建物の住宅ローンに一本化する方法があります。
土地先行融資やつなぎ融資は住宅ローンとは違う金融商品で、手持ちの現金が足りなくても、土地を先行購入することが可能です。
ただし、土地先行融資やつなぎ融資は住宅ローンより金利が高く、手数料などもかかるため費用負担は大きくなります。
③分割融資で土地と建物の費用をまとめて借りる
ローンで土地を購入する場合でも、「分割融資」によって土地と建物の費用をまとめて借りる方法もあります。
一般的な住宅ローンは注文住宅の完成時に融資が実行されるため、土地の先行購入には利用できません。
一方、分割融資は土地購入時に1回目の融資が実行され、注文住宅の引き渡し時に残金が融資される仕組みです。
分割融資なら、土地と建物の借入を金利が低い住宅ローンに一本化できるのがメリットです。
ただし、扱っている金融機関が限られるため、住宅ローンの選択肢が少なくなる点は注意すべきデメリットです。
注文住宅の住宅ローンを組むときの流れ

続いて、注文住宅のローンを組む時の一連の流れをチェックしておきましょう。
全体の流れを把握しておけば、どのタイミングで何をすれば良いのか分かり、注文住宅づくりがスムーズなります。
①土地・建物の予算を決める
住宅ローン計画では、まずどれくらいの予算をかけるのか大まかに決めましょう。予算が分からないと、用意する頭金や借入総額の予測がつかず、住宅ローン計画を立てられません。
まずは、注文住宅の土地・建物の費用相場を把握しましょう。注文住宅は定価がないため、建てるエリアや仕様で費用が変動しますが、基準がまったくないと予測が難しいです。
こちらのコラムで注文住宅の費用相場や、価格帯ごとの間取り実例を紹介していますので、参考にしてみてください。
また、ご自身の年収から、無理なく購入できる注文住宅の予算目安を計算しておくことも大切です。マイホームと年収の比率をあらわす「年収倍率」は、6~7倍が一般的。
仮に年収600万円の方なら、3,600~4,200万円が平均的な予算になるということです。
また、年収と住宅ローン年間返済額の比率をあらわす「返済負担率」も予算決めの参考になります。
返済率負担は20~25%が理想的と言われているため、仮に年収600万円なら年間返済額の目安は120~150万円。
年収から住宅ローンの借入額を考える方法はこちらのコラムで詳しく解説しています。
ただし年収倍率や返済負担率はあくまでも目安で、実際に注文住宅の予算や住宅ローンの返済額を決める際は、ライフスタイルや将来の出費なども踏まえて考える必要があります。
後半で注文住宅の住宅ローンシミュレーション例も紹介しますので、そちらも参考にしてみてください。
②仮審査をする
大まかな予算が決まったら、金融機関に住宅ローンの仮審査を申し込みます。金融機関によっては事前審査と呼ぶこともありますが、意味は同じです。
一般的にはハウスメーカーや工務店から概算見積もりを取り、仮審査を申し込むケースが多いです。
しかし、仮審査に見積書が必要ない金融機関もあり、予算が分かっていれば早めに申し込めます。
仮審査はいつでも申し込みでき、費用も発生しないため、予算の目安がついたら早めに実施しておくのがおすすめです。
もし希望金額で審査が通らなかった場合も、早めの段階ならプランを修正しやすくなります。
③住宅会社とプランをつくり込む
希望の予算で住宅ローンの仮審査が通ったら、注文住宅を建てる住宅会社と、さらにプランをつくり込んでいきます。
プランをつくり込む前に仮審査をしておくことで、本審査が通らず大幅にプランが変更になるリスクを軽減できます。
土地や建物の仕様を決めて費用総額を確定させたら、次の本審査に進みましょう。
④本審査をする
注文住宅の仕様と金額が確定したら、金融機関に本審査を申し込みます。正式審査と呼ばれることもあります。
本審査は必要書類に工事請負契約書が含まれているため、工務店やハウスメーカーと契約を結んだ直後に申し込むのが一般的です。
本審査の申し込みが遅くなると、着工も遅れてしまうためなるべく早めに手続きしましょう。
本審査が通ったら、借入額や返済方法などを決定した後、ローン契約を結びます。
⑤つなぎ融資や分割融資で土地を購入する

土地も住宅ローンに含めて購入する場合、前述したようにつなぎ融資や分割融資で支払うのが一般的です。
住宅ローンの融資実行は注文住宅の引き渡し時になるため、土地は現金で支払うか、別のローンを組む必要があるのです。
また、注文住宅の手付金・着工金・中間金なども、現金を使いたくない場合はつなぎ融資か分割融資を利用します。つなぎ融資・分割融資の詳細はこちらのコラムをごらんください。
⑥引き渡しと同時に住宅ローンの融資が実行される
注文住宅が完成したら、引き渡しと同時に住宅ローンの融資が実行されます。
当日に金融機関から住宅ローンの金額が振り込まれるため、引き渡し日は土日に設定できない点に注意が必要です。
尚、住宅ローン減税を利用する場合は、入居した翌年の2月16日頃から3月15日頃の間に確定申告を行います。
確定申告が必要なのは初年度のみで、2年目以降は年末調整等の手続きで住宅ローン減税を適用できます。
注文住宅の住宅ローンの必要書類

注文住宅の住宅ローンを組むにあたり、必要な書類をチェックしておきましょう。
仮審査・本審査の際に必要な書類を早めに用意しておくと、手続きをスムーズに進められます。
仮審査に必要な書類
- 本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
- 源泉徴収票や納税証明書など収入が分かるもの
- 残高証明書(自動車やカードのローンがある場合)
- 土地の資料や注文住宅の見積書
住宅ローンの仮審査にあたり必要になる書類はそれほど多くありません。
ただし、金融機関や申し込む方の状況によっては、ほかの書類が必要になることもあるので必ず確認してください。
自動車などほかのローン残債があると審査に影響するので、残高証明書を発行してもらい提出しましょう。
購入する予定の土地や注文住宅の見積もりは金融機関によっては必須ではないので、金額が確定する前でも仮審査を申し込めます。
本審査に必要な書類
- 本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
- 源泉徴収票や納税証明書など収入が分かるもの
- 土地の資料や注文住宅の見積書
- 印鑑(実印)/印鑑登録証明書
- 住民票
- 健康保険証
本審査では、仮審査のときより必要な書類が多くなります。印鑑登録証明書や住民票など、改めて用意しなければならないものもあるため、早めに準備しておきましょう。
また、本審査では土地の資料や注文住宅の見積書など、金額が分かる資料が必須となります。
注文住宅の住宅ローン支払いはいつから?

注文住宅の引き渡し日に住宅ローンの融資が実行されると、2か月以内に最初の支払いが始まるケースが多いようです。
引き渡し日から引っ越しまで時間がかかる場合、前の家の家賃と支払いが重なり生活が圧迫される可能性もあるので要注意。
初回の支払い日は金融機関によって異なるため、いつになるのか必ず確認して、口座にお金を用意しておきましょう。
注文住宅の住宅ローンの金利の種類

注文住宅の住宅ローンは複数の金利タイプがあり、それぞれメリット・デメリットがあります。
どの金利タイプが合っているかは人によって異なるため、違いを把握しておきましょう。
全期間固定金利型
全期間固定金利型は、住宅ローンの返済期間中ずっと金利が変わらないタイプです。
借入する段階で総返済額が確定し、安定した返済計画を立てられるのが全期間固定金利型のメリット。金利変動によって返済額が増えて、生活を圧迫する心配がありません。
ただし、固定金利型の住宅ローンは金利が高く設定されているのがデメリット。金利が上昇しなかった場合は、変動金利型の方が総返済額を抑えられる可能性があります。
全期間固定金利型のメリット・デメリットは、こちらのコラムで詳しく解説しています。
変動金利型
変動金利型は、返済期間中に金利が見直され変動するタイプです。
固定金利型より金利が低く、借入時点の総返済額を抑えられるのが変動金利型の大きなメリットです。
ただし、金利が上昇すると毎月の返済負担が増えてしまうため、返済計画を立てにくいのがデメリット。一般的に、半年ごとに金利が見直され、総返済額が変動します。
変動金利型のメリット・デメリットについては、こちらのコラムも参考にしてください。
期間選択固定金利型
期間選択固定金利型は、前述した固定金利型と変動金利型の特徴を併せ持つタイプです。金利ミックス型と呼ばれることもあります。
一定期間は固定金利で、その後は変動・固定を選べるのが特徴です。固定期間が終了したタイミングで金利も見直されますが、市場やご家庭の状況に応じて金利を選択できるのがメリット。
例えば、注文住宅に引っ越してから生活が安定するまでは固定金利を適用して、その後は変動金利で利息を抑えるといった選択も取ることができます。
ただし、金利が大きく上昇した場合、総返済額が増えてしまうのは変動金利型と同じです。また、金利の動向をチェックして、損をしない選択をする必要もあります。
期間選択固定金利型についてはこちらのコラムもごらんください。
注文住宅の住宅ローンシミュレーション例

実際に住宅ローンを借りた場合の毎月の返済額をシミュレーションしてみましょう。
フラット35利用者調査によると、2023年の土地付注文住宅の平均費用は4,903万円でした。
頭金を入れて4,000万円の住宅ローンを組む場合を想定して、返済期間・金利の違いによる返済額の変化をシミュレーションしてみましょう。
返済期間による返済額の違いをシミュレーション
借入金額と金利の条件を固定して、返済期間の違いによる月返済額・総返済額の違いをシミュレーションしてみましょう。
- 借入金額:4,000万円
- 全期間固定金利1.5%
- ボーナス返済なし
- 元利均等返済
| 返済期間 | 月返済額/年間返済額 | 総返済額 |
|---|---|---|
| 20年 | 193,018円/2,316,216円 | 46,324,216円 |
| 25年 | 159,974円/1,919,688円 | 47,992,210円 |
| 30年 | 138,048円/1,656,576円 | 49,697,092円 |
| 35年 | 122,473円/1,469,676円 | 51,438,816 円 |
上記のように、返済期間が長くなるほど毎月の返済額は減りますが、利息の支払いが多くなるため総返済額は増加します。
収入と返済額のバランスを考え、無理のない範囲で負担が少なくなる返済計画を立てることが大切です。
例えば、年収600万円、返済負担率25%で考えると年間返済額は150万円になるため、25年以上の返済期間で考える必要があります。
金利による返済額の違いをシミュレーション
借入するタイミングや利用する金融機関の金利によっても返済額が変化するため、こちらもシミュレーションしてみましょう。
- 借入金額:4,000万円
- 返済期間:35年
- 全期間固定金利
- ボーナス返済なし
- 元利均等返済
| 金利 | 月返済額/年間返済額 | 総返済額 |
|---|---|---|
| 1.3% | 118,592円/1,423,104円 | 49,808,848円 |
| 1.5% | 122,473 円/1,469,676円 | 51,438,816円 |
| 1.8% | 128,436 円/1,541,232円 | 53,943,142 円 |
同じ借入額と返済期間でも、金利によって月返済額と総返済額は上記のように変動します。
住宅ローンを利用する金融機関は金利だけでは判断できませんが、重要な要素の1つとしてチェックしましょう。
このように、住宅ローンの返済額は返済期間や金利の変動などさまざまな要素で変わります。
また、注文住宅の費用総額によっても住宅ローンの借入額や返済額は変化しますので、住まいづくり全体の基礎知識を押さえておくことも大切です。
こちらのコラムで注文住宅づくりの基礎知識を分かりやすくまとめています。
注文住宅の住宅ローンでよくある質問
住宅ローンを組んで注文住宅を建てる際に、よくある質問をまとめました。
住宅ローンで支払えない諸費用とは?
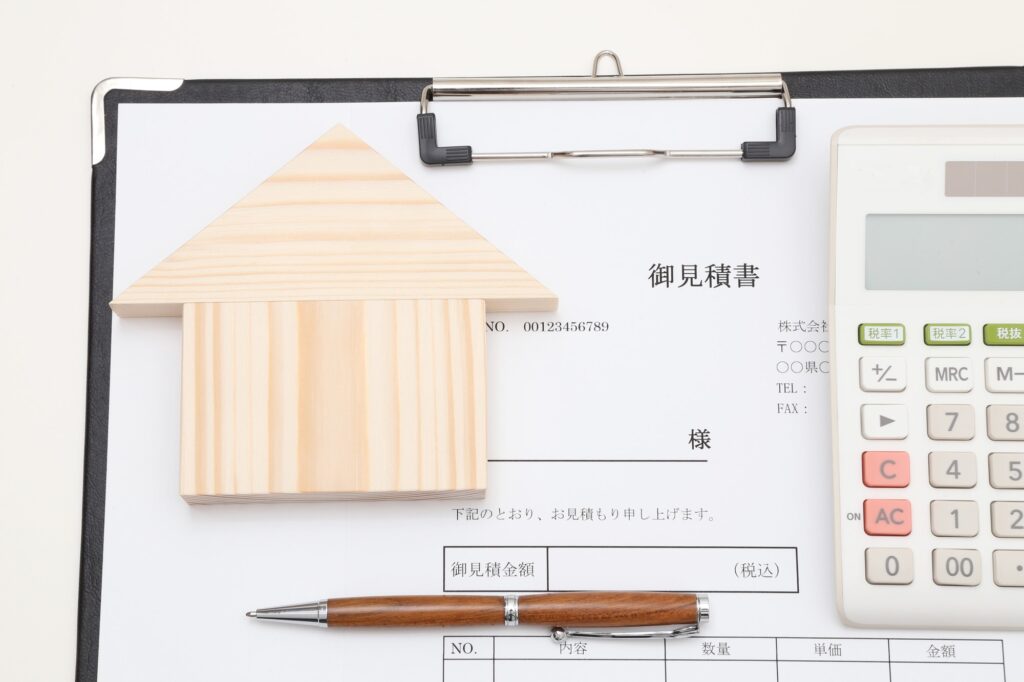
注文住宅を建てるときに必要となる諸費用の中には、住宅ローンで支払えず現金が必要となるものもあるので要注意です。
例えば、住宅ローンの手数料や地鎮祭・上棟式の費用などは、原則的に現金での支払いが必要になります。
近隣挨拶の粗品や引っ越し費用、家具の購入代金なども諸費用の一部です。
諸費用の目安は、注文住宅の総予算の10%前後で、合計すると数百万円になるため意外と負担になります。
ただし、金融機関によっては諸費用を含めて住宅ローンを組める場合もあります。仮審査を申し込む際に、どこまで住宅ローンに含められるのか確認しましょう。
こちらのコラムで注文住宅の諸費用について詳しく解説しています。
おすすめの銀行はある?

住宅ローンを扱う金融機関はさまざまな種類があり、それぞれ用意しているプランや金利などの傾向が異なります。
上記のグラフの国土交通省の調査によると、住宅ローンの新規貸出額が多いのは都市銀行や地方銀行で、多くの方が利用している傾向が分かります。
しかし、どの住宅ローンがマッチするかは人によって変わるため、一概にどの銀行がおすすめとは断言できません。
例えば、返済プランについて細かく相談したい方には、店舗が多いメガバンクや地域に密着した地方銀行のメリットが大きいでしょう。
しかし、金利の低さや手間の少なさを重視するなら、WEB上で申し込みできて金利が低い傾向があるネット銀行の方が向いています。
前述した諸費用を住宅ローンに含められるかなども金融機関によって異なるため、ご自身の条件に合うか見極める必要があります。
まとめ
住宅ローンの計画や手続きは、注文住宅づくりと平行して進める必要があります。スムーズに進めるためにも、全体の流れや基礎知識をしっかり覚えておきましょう。
注文住宅の予算と合わせて、無理のない住宅ローン計画を立てることも必要です。どれくらい借りられるのか、いくら必要なのかなど、不安に感じたら家づくりのプロに相談してみましょう。
クレバリーホームは全国のモデルハウスで、住宅ローンや資金計画に関するご相談も受け付けています。ぜひお近くのモデルハウスに、お気軽にご来場ください。