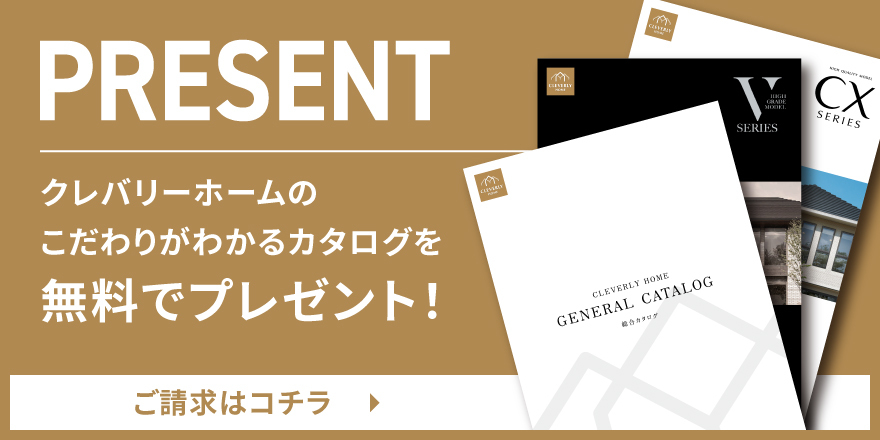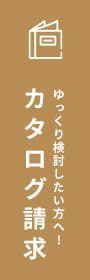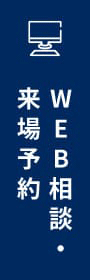ビルトインガレージは固定資産税が高くなる?計算方法や税額を抑えるコツを解説

注文住宅にビルトインガレージをつくる際、固定資産税の負担について気になる方が多いようです。
固定資産税は毎年かかるランニングコストですから、ビルトインガレージの間取りや建築費用と同じように気になるポイントですよね。
そこでこの記事では、ビルトインガレージにかかる固定資産税の計算方法や、負担を抑えるためのコツを詳しく解説します。
ガレージのある注文住宅を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
目次
まずは固定資産税の基礎知識をおさらい

ビルトインガレージの固定資産税について詳しく掘り下げる前に、まずは基本的な仕組みについておさらいしておきましょう。
固定資産税とは、土地や建物などの固定資産に対して毎年課税される地方税の一種です。
新築注文住宅の場合、土地の地価や家屋調査の結果をもとに固定資産税が決定し、以降は3年に1度税額の見直しが行われます。
注文住宅の固定資産税についてこちらのコラムでも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
ビルトインガレージは、建物の一部とみなされる場合に固定資産税がかかります。
次の章から、固定資産税がかかるガレージの条件について詳しく見ていきましょう。
どんなガレージに固定資産税がかかる?

外壁分断性・定着性・用途性の3つの条件をすべて満たしているビルトインガレージには、固定資産税がかかります。
具体的にどのような条件なのか1つずつ見ていきましょう。
外気分断性
屋根や壁で雨風をしのげる状態=外気分断性があるビルトインガレージは、建物の一部とみなされ固定資産税の課税対象になります。
一般的なビルトインガレージは、周囲を壁に囲まれて天井で雨風をしのげるため、外気分断性があると判断されます。
シャッターなしで前方が開口部になっているビルトインガレージも同様です。
ちなみに、屋根だけのカーポートは周囲の壁がないため、外気分断性はなく固定資産税もかかりません。
定着性
一般的なビルトインガレージは土地への定着性があるため、固定資産税の課税対象となります。
定着性とは、土地に建物が固定されて簡単に移動できない状態のことを指します。
ビルトインガレージは建物と同様、基礎で土地に固定されていて移動はできないため、定着性があると判断されます。
一方、地面に固定せず移動できるバイクガレージなどの場合は、定着性がないため非課税になることが多いです。
用途性
ビルトインガレージが特定の目的のためにつくられている=用途性があると判断された場合も、固定資産税がかかります。
ビルトインガレージは車を保管するという目的のためにつくられているため、用途性があると判断されます。
「1/5容積率の緩和特例」は固定資産税とは無関係

ここまで見てきたように、一般的なビルトインガレージは建物の一部とみなされるため原則的に固定資産税がかかります。
しかし、一部では「1/5容積率の緩和特例」を適用するとビルトインガレージに固定資産税がかからないと紹介している情報もあります。
結論としては、1/5容積率の緩和特例は固定資産税とは関係がないため、ビルトインガレージの税額を安くすることはできません。
1/5の容積率の緩和特例とは、延床面積の5分の1を上限として、ガレージ部分を容積率の計算から除外できる制度のことです。
ガレージ部分を容積率の計算から除外することで、敷地を有効活用して延床面積を確保できるのがこの特例のメリットです。
ただし、計算から除外できるのはあくまで容積率のみで、固定資産税の評価からガレージは外れません。
前述した外気分断性・定着性・用途性を満たすビルトインガレージの固定資産税は、基本的には免除を受けることはできませんので注意しましょう。
ビルトインガレージの固定資産税はいくら?計算方法を確認

ビルトインガレージの間取りを検討するとき、毎年どれくらいの固定資産税が気になるポイントですよね。
しかし、固定資産税の評価は基本的に建物全体でするため、ガレージ単体で税額を計算することはできません。
ただ、ビルトインガレージをつくることで、どれくらい税額が変わるのか分からないと計画を立てにくいですよね。
そこで、注文住宅の基本的な固定資産税の計算方法をもとに、ビルトインガレージ部分の建築費用が300万円かかったと暫定して、税額をシミュレーションしてみましょう。
- 「課税標準額(固定資産税評価額)×税率(1.4%)」
建物の固定資産税は上記の計算式で算出でき、課税標準額は建築費用の5割程度が目安と言われています。
- 150万円(建築費用の5割)×1.4%=2.1万円
上記の計算から、ビルトインガレージ部分の固定資産税は2.1万円となります。
ただし、新築住宅は完成から3年間は固定資産税が1/2に減額されるため、3回分の税額は1.05万円です。
また、固定資産税は3年毎に評価額を見直して税額を再計算するため、建物部分の金額は徐々に下がっていきます。
これはあくまで固定資産税の基本的な仕組みと計算式からのシミュレーションですが、1つの目安として参考にしてみてください。
ビルトインガレージの固定資産税を抑えるポイント

最後に、ビルトインガレージの固定資産税を抑えるポイントを2つご紹介します。
毎年の固定資産税の負担を抑えるために、ぜひ参考にしてみてください。
木造で建てる
ビルトインガレージの固定資産税を抑えるには、基本的に木造で建てるのが効果的です。
例えば、広い柱スパンの大開口のビルトインガレージをつくるために、鉄骨造や鉄筋コンクリート造を選ぶと、建築価格が高くなり固定資産税も増えてしまいます。
また、鉄骨造や鉄筋コンクリート造などの非木造住宅は、税制上の仕組みで木造より耐久性が高いと考えられているため、築年数による固定資産税の下落幅も少ないです。
1階にビルトインガレージをつくる場合、耐震性が気になる方も多いようですが、木造でも十分地震に強い家を建てることができます。
こちらのコラムで木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造の違いについて詳しく解説しています。
不要な設備を選ばない
固定資産税を抑えるなら、ビルトインガレージの使い勝手は確保しつつ不要な設備を選ばないようにするのもポイントです。
ビルトインガレージに高額な設備や建材を追加すると、評価額が上昇し固定資産税が増える原因になります。
例えば、リモコンで開閉できる電動シャッターは便利ですが、資産価値が高いと見なされ固定資産税評価額が上がってしまう可能性が高いです。
もちろん、必要な設備は導入すべきですが、なくても問題ないものは省いた方が、建築費用と固定資産税を抑えられるため節約になります。
車の出し入れや音の問題などガレージの使いやすさについて考えつつ、必要最小限の設備でムダのないプランを考えてみましょう。
こちらのコラムで注文住宅のガレージづくりについて詳しく解説しています。
まとめ
注文住宅のビルトインガレージは、基本的に固定資産税の対象になります。
固定資産税は毎年かかるランニングコストですから、どれくらいの負担になるのか大まかに把握しておくことが大切です。
ただし、実際の固定資産税額はガレージ単体で計算するのではなく、建物全体や自治体の判断などさまざまな要素で変動します。
実際の費用・税負担については、ビルトインガレージのある家づくりに詳しいプロに相談するのがおすすめです。
クレバリーホームは全国のモデルハウスで、ビルトインガレージを含めた住まいづくりに関するご相談を受け付けています。
ぜひお気軽にご相談ください。