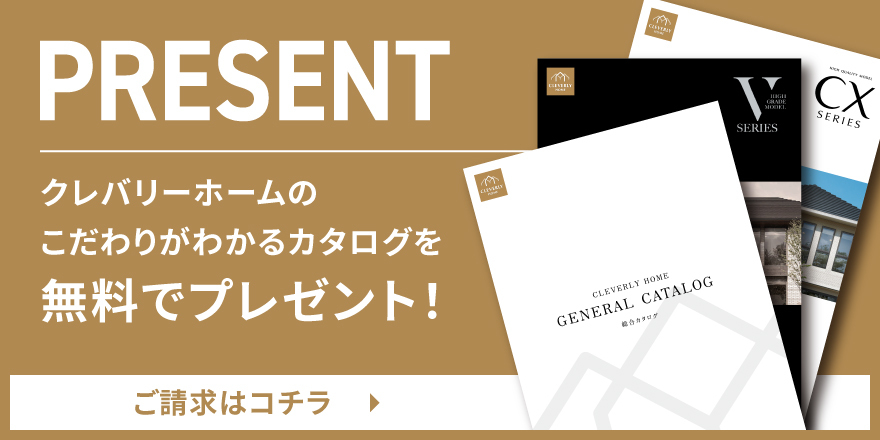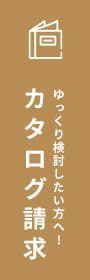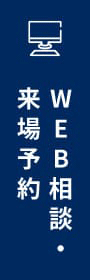注文住宅の補助金・助成金情報まとめ|国・自治体の補助金や減税制度をチェック

この記事では、注文住宅を建てるときに活用できる補助金・助成金制度や減税制度ついて詳しく解説します。
住宅関係の補助金制度は金額が大きいものも多く、うまく活用すれば初期費用を抑えるのに役立ちます。
しかし、どの補助金や減税制度が使えるのか、どうやって手続きしたら良いのかなど、不安に感じる方も多いようです。
実際、申し込み期限や書類の不備など、補助金を受け取れなくなってしまうケースもゼロではありません。
今回は、注文住宅の補助金や減税制度を使うために必要な基礎知識をまとめますので、ぜひ資金計画にお役立てください。
※本記事は2024年12月時点の情報をもとに作成しています。補助金の内容や申込状況は変動する可能性がありますので、最新の情報をご確認ください。
目次
【2024年】注文住宅の補助金・助成金一覧
この記事でご紹介する国の注文住宅の補助金・助成金を一覧表でまとめました。
どのような制度があり、いくらぐらいの補助金を受けられるのか、把握してみてください。
| 国の補助金 | 補助内容 |
|---|---|
| 子育てエコホーム支援事業 | ・長期優良住宅:100万円/戸 ・ZEH住宅:80万円/戸 |
| 給湯省エネ2024事業 | ・ヒートポンプ給湯器:8~13万円/台 ・ハイブリッド給湯器:10~15万円/台 ・家庭用燃料電池:18~20万円/台 ※給湯器の性能によって変動 |
| 戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業 | ・ZEH住宅:55万円/戸 ・ZEH+住宅:100万円/戸 ・断熱等性能等級6以上:+25万円/戸 |
| LCCM住宅整備推進事業 | ・補助上限140万円/戸 ※「設計費」「建設工事等における補助対象工事の掛かり増し費用」の合計金額の1/2 |
| 減税・優遇制度 | 補助内容 |
|---|---|
| 住宅ローン減税 | ・年度末のローン残高の0.7%を所得税から最大13年間控除 |
| フラット35金利優遇 | ・要件を満たすことで一定期間金利引き下げの優遇措置 ・例:ZEH基準:当初5年間の金利0.75%引き下げ |
| 火災保険/地震保険料の割引 | ・例:耐震等級によって保険料を10~50%割引 |
| 贈与税の優遇措置 | ・父母や祖父母など直系尊属からの贈与で注文住宅を建てる場合一定金額まで贈与税が非課税 ・質の高い住宅:1,000万円まで その他の住宅500万円まで |
注文住宅で使える国の補助金

注文住宅に関する国の補助金制度は、全国共通で使えるため積極的に検討してみましょう。
子育てエコホーム支援事業
子育てエコホーム支援事業は、エネルギー価格などの物価高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯に対し、高い省エネ性能を有する住宅の取得を支援する補助金制度です。
| 対象となる方 | ・子育て世帯または若者夫婦世帯のいずれかである ・エコホーム支援事業者と工事請負契約を締結し住宅を新築する ※子育て世帯=申請時点で2005年4月2日以降に出産した子を有する世帯 ※若者夫婦世帯=申請時点において夫婦であり、いずれかが1983年4月2日以降に生まれた世帯 |
|---|---|
| 対象となる新築住宅 | ・証明書等により、長期優良住宅またはZEH住宅に該当することが確認できる ・所有者自らが居住する ・住戸の床面積が50㎡以上240㎡以下 ・土砂災害防止法に基づく、土砂災害特別警戒区域又は災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域又は地すべり防止区域と重複する区域に限る)に原則立地しないもの ・都市再生特別措置法第88条第5項の規定※により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨の公表がされていないもの ・交付申請時、一定以上の出来高の工事完了が確認できる |
| 補助額 | ・長期優良住宅:100万円/戸 ・ZEH住宅:80万円/戸 ※市街化調整区域、土砂災害警戒区域又は浸水想定区域の場合は減額あり |
| 対象となる期間 | ・基礎工事の完了:建築着工~交付申請まで(遅くとも2024年12月31日) ・「基礎工事より後の工程の工事」への着手:2023年11月2日以降 |
| 申請期間 | ・2024年3月中下旬 ~予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで) |
※更に詳しい情報については、公式サイトでご確認ください。子育てエコホーム支援事業 注文住宅の新築
お子さまやご夫婦の年齢の要件を満たし、長期優良住宅またはZEH住宅の性能を満たす注文住宅を建てる場合に補助金を受けることができます。
補助額が大きく、住宅性能を高めることで省エネやメンテナンス費用節約効果も期待できるため、積極的に検討したい制度です。
後述するほかの国の補助金とは併用できません。しかし、地方公共団体の補助金制度で、国費が充当されているもの以外は併用可能です。
補助金の要件となる長期優良住宅・ZEH住宅の詳細は、こちらのコラムで解説しています。
給湯省エネ2024事業
効率的にお湯を沸かせる高効率給湯器の設置に対する補助金制度です。
| 対象となる方 | ・注文住宅の建築主 |
|---|---|
| 主な要件 | ・性能要件を満たし、補助対象製品として登録された高効率給湯器を設置する |
| 補助額 | ・ヒートポンプ給湯器:8~13万円/台 ・ハイブリッド給湯器:10~15万円/台 ・家庭用燃料電池:18~20万円/台 ※給湯器の性能によって変動 |
| 申請期間 | 2024年3月中下旬 ~予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで) |
※更に詳しい情報については、公式サイトでご確認ください。 給湯省エネ2024事業
エコキュート、ハイブリッド給湯器、エネファームなどの高効率給湯器に対し、1台あたりの補助額が支給される制度です。
一般的な給湯器より、お風呂やキッチンで使うお湯の光熱費を抑えられるため、補助額以上の節約効果も期待できます。
要件のハードルが低いため、どの注文住宅でも検討しやすいのもうれしいポイント。
この制度もほかの国の補助金とは併用できず、国費が使われていない自治体の補助金は併用できる可能性があります。
戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業
戸建て住宅の省エネ化を推進するための補助金制度です。
ZEHとは「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」の略で、高い断熱性能や太陽光発電などの再生可能エネルギーを創り出し、エネルギー収支がゼロになる住宅のことです。
| 対象となる方 | ・注文住宅の建築主 |
|---|---|
| 主な要件 | ・ZEH、ZEH+の交付要件を満たす住宅を新築する |
| 補助額 | ・ZEH住宅:55万円/戸 ・ZEH+住宅:100万円/戸 ・断熱等性能等級6以上:+25万円/戸 |
| 申請期間 | 一般公募(単年度事業):2024年4月26日~2025月1月7日 |
※更に詳しい情報については、公式サイトでご確認ください。令和6年度ZEH補助金
ZEH補助金は申請者の年齢に関する要件がないため、子育てエコホーム支援事業が使えない方でも検討できます。
省エネ性能や断熱性能に応じて補助額が定められており、性能の高い注文住宅を建てれば100万円以上の補助金を受けられます。
断熱性能や省エネ性能の基準を満たすZEH住宅を建てることで、光熱費の節約や快適な生活などのメリットも生まれます。
LCCM住宅整備推進事業
前述したZEH住宅よりさらに二酸化炭素の発生を抑えることを目的に、LCCM(ライフ・サイクル・カーボン・マイナス)住宅を対象とした補助金制度です。
LCCM住宅とは、住宅の建築から廃棄まで含めた全体で二酸化炭素の発生を抑える住まいのことを指します。
| 対象となる方 | ・注文住宅の建築主 |
|---|---|
| 主な要件 | 次の①~⑪のすべての要件を満たすこと
①戸建住宅の新築 |
| 補助額 | ・補助上限140万円/戸 ※「設計費」「建設工事等における補助対象工事の掛かり増し費用」の合計金額の1/2 |
| 申請期間 | 2024年5月17日~2025年1月20日 |
※更に詳しい情報については、公式サイトでご確認ください。 サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)補助金交付申請等マニュアル
ZEH住宅より要件のハードルは高くなりますが、その分補助額の上限も一戸あたり140万円と高く設定されているのが特徴です。
省エネ性能が高い注文住宅を検討するなら、ぜひ活用したい補助金制度です。
注文住宅で使える自治体の補助金

注文住宅を建てる場所を管轄する自治体によっては、独自の補助金制度を用意していることもあります。
自治体の補助金制度はさまざまな種類があるため、4つのジャンルに分けていくつかの例をご紹介します。
省エネ住宅に対する自治体の補助金
省エネ性能を高めた注文住宅に対する補助金は、多くの自治体で導入されています。
| 自治体/補助金制度 | 主な要件 | 補助額 |
|---|---|---|
| 東京都/東京ゼロエミ住宅 | ・一定の省エネ性能を持つ住宅の新築 | ・40~240万円 ※性能水準により変動 |
| 千葉県市川市/スマートハウス関連設備導入費補助金交付事業 | ・太陽光発電設備、家庭用燃料電池システム、リチウムイオン蓄電システム、エネルギー管理システム(HEMS)などの設置 | ・上限7~22.5万円/戸 ※設置機器によって変動 |
| 神奈川県/ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助金 | ・45歳以下で市内に取得価格500万円以上の新築住宅を取得する方 | ・ZEH+ 100万円/戸 ・ZEH 55万円/戸 ・ZEH Oriented 50万円/戸 |
※更に詳しい情報については、各自治体の公式サイトでご確認ください。
太陽光発電や蓄電池など、再生可能エネルギーを創り出す設備に対して、導入補助金を用意している自治体が多いです。
また、一定の断熱性を持つ住宅を対象とする補助金もあります。
移住での家づくりに対する自治体の補助金
他エリアからの移住を支援している自治体の中には、注文住宅の取得を対象に補助金を用意しているところもあります。
| 自治体/補助金制度 | 主な要件 | 補助額 |
|---|---|---|
| 北海道標津町/新築住宅支援 | ・延床面積80㎡以上の住宅を市内に新築 | ・建築工事費の10% ※補助上限200万円 |
| 群馬県千代田町/移住者住宅取得費等補助事業 | ・5年以内に住民基本台帳に登録がなく、町内に住宅を取得して10年を超えて居住する | ・土地を代金を除く購入経費の1/2 ※補助上限30~40万円 |
| 鹿児島県薩摩川内市/定住住宅取得補助金 | ・市内業者を利用し指定地域内に200万円以上の住宅を新築 | ・20~100万円/戸 ※中学生以下の子育て世帯は加算あり |
※更に詳しい情報については、各自治体の公式サイトでご確認ください。
補助対象となる住宅の要件や補助額はさまざまですが、北海道標津町のように補助上限200万円と大きい制度もあります。
注文住宅を建てるエリアを決めるときは、自治体の移住支援制度もチェックしてみましょう。
二世帯同居や子育て世帯に対する自治体の補助金
親世帯と二世帯同居や近居をするために注文住宅を建てるケースも、自治体の補助金対象になることが多いです。
| 自治体/補助金制度 | 主な要件 | 補助額 |
|---|---|---|
| 神奈川県厚木市/親元近居・同居住宅取得等支援事業補助金 | ・親世帯が1年以上厚木市に居住しており、近居・同居のため市内に住宅を取得 | ・近居40万円:同居60万円 ※子育て世帯やエリアによって加算額あり |
| 埼玉県蕨市/三世代ふれあい家族住宅取得補助金 | ・同居または近居のために市内に取得する住宅 | ・住宅取得費用の1/100分相当額 ※補助上限10万円 |
| 千葉県千葉市/三世代同居・近居支援事業 | ・千葉市内で親と子と孫の3世帯が1km以内に同居するための住宅の新築 | ・上限50万円/戸 ※市内業者の施工の場合上限100万円 |
※更に詳しい情報については、各自治体の公式サイトでご確認ください。
親子世帯が同居する二世帯住宅だけでなく、近くに注文住宅を建てる同居の場合も補助金の対象になるケースがあります。
また、子育て世帯の方を対象に補助金の加算額を設けている場合も多く、注文住宅の費用負担軽減に効果的です。
地元木材を使用した家づくりに対する自治体の補助金
環境保護や地域促進の観点から、地元の木材を使用した注文住宅を対象とする補助金を用意している自治体もあります。
| 自治体/補助金制度 | 主な要件 | 補助額 |
|---|---|---|
| 東京都檜原村/地場産材利用促進事業 | ・地場産材を3㎥以上使用する木造住宅を市内に新築 | ・1㎥あたり2万円 ※補助上限50万円 |
| 静岡県浜松市/天竜材新築補助金 | ・浜松市内で製材・加工された天竜材(FSC認証材)を一定量使用して市内に新築 | ・1㎥あたり2万円 ※補助上限40万円 |
| 佐賀県/県産木材を使用した新築・リフォーム補助 | ・県産木材を一定量以上使用し県内に新築 | ・30万円/戸 |
※更に詳しい情報については、各自治体の公式サイトでご確認ください。
県や市町村の地元産木材を一定量使用することで、一定の補助金が支給される制度が多いです。
地元の気候で育った高品質な木材を使用することは、耐久性などの面でもメリットがあります。
注文住宅の減税/優遇制度

注文住宅の減税制度や優遇制度を活用した費用負担を軽減する方法もあります。
住宅ローン減税
住宅ローン減税は、年度末のローン残高の0.7%を所得税から最大13年間控除する仕組みです。
※住宅ローン控除:2024年入居の場合
| 控除率 | 0.7% | ||
|---|---|---|---|
| 控除期間 | 13年間 ※一般住宅は10年 |
||
| ローン残高・控除額の上限 | 認定長期優良・低炭素住宅 | 4,500万円 | 子育て世帯・若者夫婦世帯 5,000万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 子育て世帯・若者夫婦世帯 4,500万円 |
|
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 子育て世帯・若者夫婦世帯 4,000万円 |
|
| 省エネ基準に適合しない 「その他の住宅」 |
0円 | ||
※子育て世帯・若者夫婦世帯:「19歳未満の子を有する世帯」又は「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」
参照:国土交通省 住宅ローン減税
上記のように住宅性能によって借入限度額と、1年間の最大控除額が決められています。例えば、ZEH水準の住宅で3,500万円以上の住宅ローンを組んだ場合、初年度は24.5万円が所得税などから控除されます。
フラット35金利優遇
住宅金融支援機構の住宅ローン、フラット35は、省エネ性、耐震性、バリアフリーなどの要件を満たすことで、金利を一定期間引き下げる優遇措置を用意しています。
例えば、ZEH基準の注文住宅は、当初5年間の金利が0.75%引き下げられます。(2024年12月時点)
参照:【フラット35】S
また、お子さまの人数によって一定期間金利を引き下げられる優遇措置もあります。
お子さま1人の場合は当初5年間金利を0.25%引き下げ、2人の場合は0.5%、といったようにお子さまの人数が多いほど金利が優遇されます。(2025年3月31日までの申込受付分に適用)
支払総額がかなり変わる場合もあるので、補助金と併用して活用したいですね。
火災保険/地震保険料の割引
耐火性能や耐震性能を高めた注文住宅は、火災保険や地震保険料の割引を受けられるケースもあります。
例えば、地震保険は耐震等級によって、10~50%の割引率が設けられています。
火災保険や地震保険料は毎年のランニングコストですから、長く暮らすほど節約効果も大きくなるのがメリット。
贈与税の優遇措置
ご両親から資金援助を受けて注文住宅を建てる場合、贈与税の優遇措置で負担を軽減できるケースもあります。
| 非課税限度額 | 質の高い住宅※ | 1,000万円 |
|---|---|---|
| 一般住宅 | 500万円 | |
| 適用期限 | 2026年12月31日まで | |
※質の高い住宅
1.断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上
2.耐震等級2以上又は免振建築物
3.高齢者等配慮対策等級3以上
注文の性能によって非課税限度額が異なり、性能が高い住宅は1,000万円まで、一般住宅は500万円まで贈与税がかかりません。
参照:No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
2025年以降の注文住宅補助金は?

ここまでご紹介した注文住宅の補助金は、2024年12月時点のもので、2025年以降継続するか決まっていない制度もあります。
前年度の補助金の継続、廃止は運営する国や自治体によって変わり、要件が変更になるケースも。
2025年の補助金については、年度が切り替わる4月前後に公表されることが多いため、定期的に国や自治体のホームページなどをチェックしましょう。
ただし、来年度の補助金情報を待ってから注文住宅づくりを始めると、タイミングを逃してしまう事もあるので要注意。
条件の良い補助金があっても、良い土地の購入タイミングを逃したり、建築費用の高騰でかえって高くついたりするリスクがあります。
補助金ありきで家づくりのタイミングを考えるのではなく、ライフスタイルに合わせて計画を進めて、その時点で利用できる制度を検討するのがおすすめです。
クレバリーホームのモデルハウスでは、補助金活用も含めた住まいづくりのご相談を受け付けていますのでお気軽にご相談ください。
注文住宅の補助金を活用するメリット・デメリット

まずは、注文住宅づくりで補助金を活用するメリット・デメリットについて詳しくチェックしておきましょう。
メリット
注文住宅の補助金制度は原則的に返済不要なため、建築費用を抑えられるのが大きなメリットです。
補助額は制度によって異なりますが、子育てエコホーム支援事業のように最大100万円の補助金も。
デメリット
注文住宅の補助金を受け取るためには、一定の要件を満たす必要があり、建築費用が高くなるケースが多いのがデメリット。
長期優良住宅やZEH住宅などの基準を満たすためには、断熱性や耐久性などを高める必要があります。
ただし、住宅性能を高めることで快適な生活や光熱費の削減などのメリットがあり、長い目で見れば損にはなりません。
補助金を活用して住宅性能を高めれば、長く暮らすほどお得になります。
初期費用が少し多めにかかるのはデメリットですが、住宅ローンや資金計画のハードルをクリアできれば損にはならないということです。
注文住宅の補助金は併用できる?

今回ご紹介したように注文住宅の補助金制度は複数ありますが、併用できるかどうかはケースバイケースです。
基本的に、国の補助金は併用できないことが多いです。また、都道府県や市町村の補助金も、国費が使われている場合は国の補助金と併用できません。
一方、国の補助金と、国費が使われていない自治体の補助金は併用できるケースもあります。
補助金のホームページなどに併用可かどうか記載されていますが、細かい情報をすべて調べるのはなかなか大変です。
補助金に詳しい住宅会社に相談し、どの制度が良いか、併用できるかなど相談するのが良いでしょう。
注文住宅の補助金活用時の注意点

補助金を活用して注文住宅計画を立てるときは、次のようなポイントに注意しましょう。
予算上限による早期締め切り
注文住宅に使える補助金制度は、予算上限があり申し込み期限より早く締め切られてしまうことが多いので注意が必要です。
申し込み期間だけを見て計画を立ててしまうと、予算上限に達して補助金枠が無くなってしまう可能性があります。
いつ締め切りになるかは申し込み状況によりますので、なるべく早めに注文住宅計画を進めるのがおすすめです。
初期費用は全額用意する必要がある
注文住宅の補助金は竣工後に支給されることがほとんどなので、初期費用は全額用意する必要がある点にも要注意です。
補助金を引いた金額で資金計画を立ててしまうと、お金が足りず慌てて用意することになるかもしれません。
補助金が支給されるタイミングを確認して、無理のない資金計画を立てましょう。
登録事業者でないと申請できないこともある
補助金によっては登録事業者でないと申請手続きができず、希望の住宅会社で建てられないケースもあります。
また、補助金は一度登録事業者に入ってからお施主様に振り込まれる場合もあり、申請代行費用が差し引かれる場合も。補助金について相談する際、代行費用がかかるのかなど確認しておきましょう。
一定の基準を満たす必要がある
国や自治体の補助金・助成金を受けるためには、注文住宅の性能や設備など一定の基準を満たす必要があることも注意点です。
申請要件を満たせないハウスメーカーや工務店だと、補助金を受けることができません。
しかし、注文住宅を建てるハウスメーカーや工務店選びの際は、補助金のことだけでなく予算やデザインなどさまざまな点を考える必要があります。
こちらで注文住宅づくりに必要な基礎知識を分かりやすくまとめていますので、あわせて参考にしてください。
まとめ
注文住宅に使える補助金や優遇制度は複数あり、建てるエリアや仕様によって適切な制度が変わります。
まずはどんな補助金があるのか把握し、ご予算や理想の注文住宅と照らし合わせながらどの制度を活用するか考えましょう。
ご自身で判断するのが難しいときは、住まいづくりのプロに相談するのがおすすめです。
クレバリーホームの全国のモデルハウスでは、補助金活用を含めた資金計画もご相談いただけます。ぜひお近くのモデルハウスにご来場ください。